日本語 English
about
世界は、曖昧で、その輪郭はぼやけている。
見ていたはずのものはそこにはなく、意味を求めた先に、ただ沈黙があることもある。
私は、そんな揺らぎのなかで、絵や言葉に触れて、「存在とは何か」という問いに向き合っています。
Statement
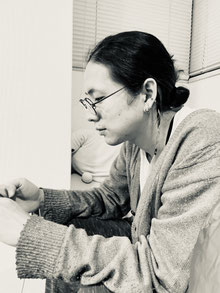
私は幼少の頃より「なぜ自分がここに在るのか」「なぜ世界が在るのか」と、ぼんやりと考え続けています。仏教、宇宙論、量子論、生物化学、哲学など複数の領域を横断しながら思索を続け、私は世界が不確かで曖昧で流動的なものだという感覚を強く持つようになります。物質と呼ばれるものから生物、国家、芸術、私自身に至るまで、全ては出来事の連続によって成り立つ関係の束に過ぎないのではないか。そのような世界観が、私の制作の根幹にあります。
今日、仮想現実や拡張現実、生成AIによって作られた画像や動画、フェイクニュースなどの「虚構」とされるものが日常に浸透し、まるでSFの如く虚構と現実の境界が曖昧になってきています。
しかし、それは決して今に始まった現象ではありません。
約7万年前に起きた認知革命以降、人類は神や国家、企業、経済、芸術、言語、数式といった「実体を持たない想像」を共有し、それを現実の土台として文明を築いてきました。私たちは、虚構によって結びつき、時に争い、進化してきました。
では、
虚構とは“存在しない”ものなのか。
現実とは“存在する”ものなのか。
そもそも“存在”とは一体なんなのか。
これらの問いは、私の作品を通して繰り返し立ち現れてきます。
量子論の視点では、私たちが「物質」として捉えているものですら、実体を持つものではなく、場の揺らぎや確率的な存在の重なりとして理解されています。世界を記述する最小単位とされる素粒子は粒子と波の二重性を持ち、その境界は曖昧で、それ自体が一つの出来事のような性質を持ちます。私は、そうした非実体的な要素が、互いに関係し合うことでネットワークを形成し、その構造そのものが「世界」であり「自分」であると捉えています。そこには虚構と現実の差異などほとんどありません。
その思想は、私の制作の在り方にも色濃く反映されており、作品の精緻に構築されたかのような静けさの奥には、常に揺らぎと曖昧さが漂っています。
「empty」シリーズでは日本画の技法を基盤としながら、岩絵具や墨、アクリル絵具、樹脂やウレタン、メッキといった素材をときに混在させながら使用します。この作品群の主軸となる図像的構成は、「海」「砂漠」「煙」「雲」「樹皮」「細胞」等のイメージを古典芸術からマンガ・アニメ、CG表現に至るまで、現地で観察し、写真を撮り、web上から拾い集め、その素材が「上と下」「マクロとミクロ」といった視点で織り混ざるように構成されています。そこにはパースペクティブの消失、または点在が生じます。そして、私は意識と無意識の中間に立つように心がけ、それを描きます。
「存在についての抽象画」シリーズでは私の存在論についての思索を直接的に提示しています。文章を主媒体としながらも絵画として描くことを強く意識して制作しています。文章としてそれを読むときは絵画としての要素はすり抜けていき、絵画として観るときは文章の内容がすり抜けていきます。「見る/読む」「意味/形態」「情報/物質」といった二項の境界を揺らがせます。
私は、実体の不確かさと、関係の中に生まれる現実、そして虚構と現実の連続性の中で、「存在とは何か」という根源的な問いを、作品を通じて繰り返し立ち上げていきたいと考えています。
concept of art works
「empty」シリーズ
「empty」とは[空っぽの~、中身のない~]といった意味を持つ形容詞です。しかし、このシリーズにおいてのそれは単なる欠如ではありません。
意味や本質というものはその“物”に宿っているわけではなく、物と人、そして環境との関係性の中に生じるものです。このシリーズは「Landscape」「Photography」「Framework」「形」といったサブシリーズを含みますが、そのいずれにおいても、存在と曖昧さが関係性によって立ち現れるような構造を意識しています。
「存在についての抽象画」シリーズ
言葉を主媒体としたこのシリーズに「抽象画」というタイトルが付くことに違和感を覚えるかもしれません。言葉は一般に明確な意味を持った“具象的な表現”と捉えられがちです。しかし、実際には言葉とはかなり抽象度の高い表現、記号そのものです。インクの染みや音という物理的な現象に恣意的な意味を与え、その意味は使用者の文脈や文化に依存し、対象との間に必然的な結びつきはありません。それは現実を直接的に表すことは出来ず、常に翻訳された“何か”なのです。
history
1994
石川県金沢市に生まれる
2021
株式会社Sandwichに制作アシスタントとして入社
学歴
2016
京都芸術大学 日本画コース 卒業
2018
京都芸術大学 大学院 ペインティング領域 修了
受賞歴
2018
大学院 修了展「優秀賞」受賞
「画心展2018 -Selection Vol.15-」優秀賞受賞(佐藤美術館 / 東京)
2019
「ZEN展」優秀賞受賞(東京都美術館 / 東京)
2020
「UNKNOWN ASIA 2020 ONLINE」レビュアー賞 ×1 受賞
展覧会歴
2018
「シュレディンガーの猫展」(東京都美術館 / 東京)
「画心展2018 -Selection Vol.15-」(佐藤美術館 / 東京)
2020
「Artistsʼ Fair Kyoto 2020」入選(京都文化博物館 / 京都)
「IAG AWARDS 2020」入選(東京芸術劇場 / 東京)
「UNKNOWN ASIA 2020 ONLINE」出展
2022
「ART GOSE ON -Session 3 / MOVE ON (Yes, art goes on)-」(SEASIDE STUDIO CASO / 大阪)
個展「-それは波としてそこに現れる-ψ」(STUDIO DIFFUSE MAKE+ / 大阪)
2024
個展「曖昧」(GALLERY Ami - Kanoko / 大阪)
「静寂と喧騒、神話と禅境 - 台湾と日本の膠彩画家による合同展 -」(外琨塔 Vaikuntha 藝術中心 / 台北)
2025
「余白のアートフェア / MARGINAL ART FAIR 福島広野」(二ツ沼総合公園 / 福島)
「WHATZ ART FAIR 台北 2025」 出展 (台北シェラトングランドホテルホテル / 台湾)